ブログ
2025.07.01
会ったことのない相続人との遺産分割協議はどのように進めていくのかを実際の事例を基にご紹介
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。とうとう7月に入ってしまいましたね。東海地方の梅雨明けはまだですが、西日本は既に梅雨明けして夏本番がきています。梅雨の湿った天気は嫌いですが、梅雨明けが早すぎると水不足も心配になってきますよね。
さて、本日は近年増加していると感じる相続手続についてです。ひと昔前は相続が発生した際に相続人の代表者の方に他の相続人の所在や連絡先を確認すればだいたいは連絡がついたものです。
たまに故人に隠し子(認知した子)がいたりするケースもありますが、これはこれでよくある話しではあります。
ただ、近年は再婚者数の増加もあり、先妻との間の子がいたり、兄弟姉妹間の相続で代襲相続が発生してしまったりすると、住所や連絡先が全くわからない相続人という方がでてきます。
ただ、そうした住所や連絡先がわからない相続人がいるからといって、故人が遺言書等で事前準備をしていない場合は、そうした相続人を無視して相続手続を進めることはできないため、相続人全員を探し出して遺産分割協議を行う必要があります。
今回はそうした住所や連絡先のわからない相続人がいる場合に士業等はどのように遺産分割協議をまとめ、預貯金等の解約手続を進めているのかを実際の事例を基にご紹介していこうかと思います。
相続人代表者との面談
先日、いつも直葬の手配でお世話になっている葬儀社の方より、葬儀が終わったご遺族が相続手続で困られているようなので、相談に乗ってもらいたいという連絡がありました。
さっそく、ご遺族の方へと連絡を取り、面談させて頂いたのですが、故人は再婚者であり先妻との間にお子様がいるとのことです。
相談者から見れば、異母兄妹がいるという状況です。
※故人(被相続人)は父
※相続人は依頼者及び会ったことも無い異母兄妹たち
ただ、異母兄妹がいるという事は知っていても、その異母兄妹とは会ったこともないため、当然、現在の住所や連絡先などもわかりません。
故人の財産としての預貯金を解約しに行こうと銀行へ行ったところ、「遺言書がないのでしたら、異母兄妹を含めた遺産分割協議書の提出又は異母兄弟の署名捺印と印鑑証明書の提出が必要」と言われて、住所も連絡先も知らない異母兄弟をどうやって見つけたらいいのだ?と、八方ふさがりの状況で故人の葬儀を担当してくれたスタッフへと相談されたというのが、当協会へ相談が来た経緯のようです。
通常、故人が遺していた預貯金については故人が死亡した事実を金融機関へと伝えると「口座凍結」の処置がされて、以降、引き落とし等ができなくなります。
この名義人死亡に伴う「口座凍結」を解除するには、故人の遺言書を提示するか相続人全員の遺産分割協議書を提示する必要があります。(銀行が用意した解約書面に相続人全員が署名及び実印で捺印して印鑑証明書を提出する方法もあります)
つまり、銀行側としては故人の財産を誰がどれだけ相続するのかはっきりしない内は解約に応じないということです。
故人が遺言書を残しており、遺言書に預貯金について誰に相続させるか記載されていれば、銀行としては故人が指定した相続人(又は受遺者)から申し出があれば解約払戻し手続きに応じます。
遺言書が無い場合は、法律上は全ての財産を相続人全員で共有している状況となります。この共有の状況のままで、相続人の中の誰かひとりに対して払い戻しをしてしまうと銀行側としても相続トラブルに巻き込まれてしまう恐れがあるため、遺産分割協議を行ったうえで、預貯金を誰が相続するのかを書いた書面(遺産分割協議書)の提出を求めることになります。(銀行側が用意する解約書面に相続人全員の署名捺印もあり)
遺産分割協議書には、間違いなく相続人がその協議内容について同意したと第三者でもわかるように「実印(印鑑証明書と同じ印)」にて捺印をすることになりますので、銀行側は遺産分割協議書と印鑑証明書のセットを提出してもらうことで、相続人全員で遺産分割が整ったということがわかる仕組みです。
ただ、銀行側では、遺産分割協議書に署名捺印している相続人が、相続人であるかどうかは把握できないため、署名捺印している人が相続人であり、かつ相続人全員での遺産分割協議がされていることを確認するために、故人と相続人の戸籍を併せて提出してもらうことで、相続人が誰であるのかを把握します。
必要となる戸籍は故人と相続人の関係によって大きく変わる為に一概には言えませんが、相続手続において戸籍集めは非常に重要な点であり、相続手続は戸籍集めから始まるといっても過言ではありません。
会ったこともない相続人の戸籍はどのように集めるのか?
一般のご家族であれば、たとえ離れて暮らしていたとしても相続に必要な戸籍や印鑑証明書については電話で連絡して相続手続を行う代表者のもとへ郵送で送ってもらえば済む話しです。
ただ、今回の事例のように住所や連絡先が不明な異母兄妹の場合ですとそもそも連絡先がわからないのですから電話を掛けることもできませんし、住んでいる場所がわからないので手紙を送ることもできません。では、どうするのか?
相続手続の実務おいてはこうした事例は決して珍しいものではないため、解決策はあります。
異母兄妹の方が通常の生活をされているのでしたら、お住まいの住所に住民登録をしています。引っ越しをする際にする転出届や転入届をちゃんとしている限りは現住所と住民票上の住所は同一となるはずです。
例外として、学生さんのように親元に住所を残したまま、ひとり暮らししている方や借金から逃げるために住所を移していないといったケースもありますが、、、
ですので、異母兄妹の電話番号がわからなくても、住所がわかれば郵送にて相続手続への協力を打診することができるわけです。
では、なんの手がかりもない異母兄弟の住所をどうやって割り出せばいいのでしょうか?住民票を取得するためには異母兄弟が住んでいる市区町村役場へと申請しなければいけませんし、そもそも異母兄弟といっても第三者に対しては戸籍や住民票は交付してもらえません。
こうした場合に士業が行っている具体的な方法としては下記のような流れとなります。
① 故人の出生~死亡までの戸籍を取得
② 先妻と異母兄妹の本籍地を確認
② 異母兄妹の本籍地にて戸籍と戸籍の附表を取得
※戸籍の附票とは、ある戸籍に記載されている人々の住所の移り変わりを記録した書類です。本籍地の市区町村で管理されており、戸籍が作られた時からの住所の履歴が記載されています。
事例のように先妻との間に異母兄妹がいる場合なら、故人の出生~死亡までの戸籍を揃えることで、戸籍の中に先妻との間にできた子供の情報がでてきます。
先妻と別れた状況が離婚のような場合でしたら、婚姻で作成された故人と先妻の戸籍から離婚を原因として先妻が別の戸籍に移っていることになります。
離婚の際に母親が親権を有しているようなら、子供も母親に従って故人(父親)の戸籍から離脱することになり、離婚した母と子供の戸籍が新たに作成されることになります。
実際に故人が死亡するまでには離婚から相当期間が経過していることも多く、離婚した際は未成年だった子供も結婚して新たな戸籍に移っていることもあるため、そうした情報を故人の出生~死亡までの戸籍の中から順番に辿っていくことで、異母兄妹の最新の戸籍にいきつくことができます。
異母兄妹の現在の戸籍(本籍地)が判明すれば、その市区町村役場に対して異母兄妹の戸籍の附表の交付申請することで、異母兄妹の現住所が判明することになりますので、その住所宛てに郵便物を送ることで相続手続をスタートさせることができるようになるという訳です。
問題になるのは、第三者である異母兄妹が戸籍や戸籍の附表を取得できるのかということですが、相続手続に必要な場合など第三者であっても戸籍等の内容を確認する正当な事由がある場合は、交付を受けることができますので、相続人の所在を確認しなければ相続手続が始められないような場合は、異母兄妹の戸籍であっても申請することで取得することができます。
遺産分割協議の打診
相続人の住所が判明した後は、実際の相続手続に移ることになりますが、まずは異母兄妹である相続人に対して、相続が発生した事と、異母兄妹が相続人になっていることを伝える必要があります。
この辺の手続については各士業事務所毎に手続の進め方は異なりますので、一概には言えませんが、一例として当協会で進める場合をご紹介します。
相続人の確定と住所が判明した後は、依頼を受けた相続人から遺産分割に関する希望の聴き取りを行います。依頼者の希望によっては、法定相続分で分割すれば良いというケースもあれば、異母兄妹には財産を渡したくないから、異母兄妹には相続分の放棄を求めるといった内容になることもあります。
また、相続する財産が現預金だけでなく不動産や株式といった有価証券も混ざっている場合は、たとえ法定相続分で分けようと考えていたとしてもきっちり等分で別けられるとは限らないので、こうした部分のどのようにしていきたいのかを依頼者と打ち合わせを行い、遺産分割協議書の案(下書)を作成します。
もちろん、異母兄妹側がこちらで作成した遺産分割案に同意するとは限りませんので、あくまで「こんな分割案で進めていきたいと考えているのですが、あなた(異母兄妹)のお考えをお聞かせください」といった感じで案内文を添えて発送することになります。
特にこれまで関わりのなかった別れた父や異母兄妹が亡くなったようなケースでは、異母兄妹側としては、特に興味もないことからすんなり同意してもらえることもあれば、面識のない異母兄妹間なら関係がこじれてしまっても問題ないと考えて徹底的に争ってくることもあります。
こればかりは、相続人間の関係や考え方によるところですので、代理で手続を行う士業としてはなんともしがたいところではありますが、なるべくスムーズに相続手続が進むように各士業事務所で工夫されるところでしょう。
相続手続に着手
遺産分割協議書案について異母兄妹が同意してくれるとなれば、正式な遺産分割協議書を再度送付して、異母兄妹の署名と実印での捺印をもらい、印鑑証明書を付けて返送してもらうことになります。
異母兄妹が受け取るべき預貯金等があるのでしたら、併せて解約払戻し手続を代理で行うための委任状を一緒に送ってもらうようにすると、何度も異母兄妹の手を煩わせる必要がなくなります。
異母兄妹が遺産分割案に同意してくれない場合は、異母兄妹の希望を確認したうえで、遺産分割協議書案を作成しなおしたうえで再度発送します。
時には感情の問題から異母兄妹が全く遺産分割協議に応じないということもありますが、こうなってしまった場合は弁護士に依頼して遺産分割調停等に進むことになります。
問題なく遺産分割案に同意してもらえて、印鑑証明書等の必要な書類も送ってもらえたなら、それら一式を携えて銀行にいくことで、銀行側も誰が預貯金を相続するのかが明確になるため、解約払戻しに応じてもらえることになり、晴れて相続手続を完了することができるといった流れとなるわけですね。
今回、相談を受けた事案でも、相続人多数にわたり戸籍の取得や住所の割り出し等にかなり時間を要しましたが、分割案については、もともと財産が預貯金しかなく、また法定相続分での分割提案であったことから、特にもめることもなくすんなりと異母兄妹の方からも同意をもらうことができました。
異母兄妹等が絡む相続手続では、依頼者側が「異母兄妹と電話で話したりしないといけないのでは?」と心配されて、二の足を踏んでいる方も多くいます。
ただ、士業に手続代行を依頼する場合は基本的に連絡のやりとりは士業事務所側で行うことになるため、今回のように異母兄妹側も特に遺産分割について注文をつけてこないような場合でしたら、異母兄妹とは一度も話さず終わってしまうことも珍しくありません。
依頼者側があまり関わりあいたく無いと考えている場合は、異母兄妹側も同じように考えていることも多く、面倒な手続が長引くよりはさっさと終わらせてしまいたいという気持ちもあるのでしょうね。
ですので、今回の事案のように「相続人の所在がわからない」「相続人の連絡先がわからない」「会ったこともない相続人とはなるべく関わりあいたくない」といった事情でお困りのケースでしたら、当協会はもちろん、相続業務を取り扱っている士業事務所へと相談してみることをお勧めします。
相続手続を放置している期間が長引けば長引くほど、その他の相続人との連絡は取り辛くなってきますので、なるべく早めに相談するようにしてくださいね。
相続手続や死後事務のことなら名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。
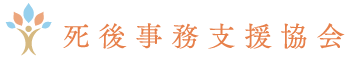


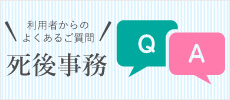

.png)
