ブログ
2025.07.04
死後事務支援を行うのに何か特別な資格がいるのか?
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。名古屋も梅雨明けしたようですが、例年に比べてもかなり早い梅雨明けのようですね、、、、。
水不足にならないと良いのですが、かといって台風やゲリラ豪雨も困りものですから、ほどほどに降ってくれないかな~。
さて、本日のテーマは、身元保証や死後事務委任の仕事を始めるのに何か特別な資格がいるのか?という内容です。
最近、一般の事業者の方から相談が増えているのですが、そうした相談(質問?)の中で増えてきているように感じるのが今回のテーマです。
恐らく、身元保証や死後事務、介護といった分野とは関係のない別の事業から参入しようと考えている方々なのだと推思われます。
では、実際のところ何か特別な資格がなければ身元保証事業や死後事務事業といったことはできないのでしょうか?今回はその点を簡単にご紹介しておきたいと思います。
誰が担える?安心を提供する事業者の要件について
近年、身寄りのない高齢者や単身者の増加とともに、身元保証契約や死後事務委任契約のニーズが高まっています。病院や施設入所の際の保証人、亡くなった後の葬儀手配や行政手続きを担ってくれる人がいない…
そんな不安を抱えた方が、専門の事業者に依頼するケースが増えているのです。では、それらの契約を受ける事業者に、特別な資格は必要なのでしょうか?
身元保証契約とは?
身元保証契約とは、病院への入院や介護施設への入所時に求められる「保証人」や「緊急連絡先」としての役割を、第三者が契約によって担うものです。これにより本人がスムーズに入院・入所できるようになります。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約は、本人の死後に必要となる葬儀・納骨・役所手続きなどの事務処理を、あらかじめ委任する契約です。誰にも迷惑をかけず、本人が望む形で人生を終えたいというニーズに応える仕組みと言えるでしょう。
弁護士や介護福祉士などの資格は必要?
結論から言うと、これらの契約を受託するにあたって、法律上必須となる資格はありません。
つまり、弁護士や介護福祉士などの国家資格を持たない一般法人・個人でも、適切な体制と倫理観をもっていれば契約を結ぶことができます。
ただし、以下のような点は重要です
契約内容の理解力と法的知識
身元保証契約や死後事務委任契約には、個人情報、財産、医療・福祉に関するデリケートな要素が含まれるため、相談対応から実際の執行手続において相続を中心としてかなり具体的な法律知識が不可欠です。
信頼性と透明性
特に死後事務に関しては、本人の意思を確実に反映するため、契約書の作成や履行において透明性と誠実さが求められます。
体制の整備
例えば、緊急時に対応可能な連絡体制や、死後の事務手続きが滞りなく実行できるような業務フローの設計が必要となります。
資格者が関わるメリット
資格がなくても契約は可能ですが、弁護士や行政書士が契約書の作成や内容チェックを行うことで、より安心できるサービスとなります。また、介護福祉士や看護師と連携している事業者であれば、医療・福祉の現場に即した支援も期待できます。
ですので、事業を行うにあたって、事業者自身が専門の資格を有している必要まではありませんが、事業を遂行していくなかでは必ず専門的な知識が必要とされる場面が出てきますので、事業者自身でそうした人材を抱えていない場合は、外部の専門家と連携しおくことは、こうした事業を行っていくうえでは必須と言えます。
おわりに
近年は、身寄りのない高齢者や単身者の増加をうけて、以前までは一部の事業者や専門家しか知らなかった「身元保証」や「死後事務委任」といった言葉も、メディア等を通して世間に認知されつつあります。
身元保証や死後事務委任の認知が進むにつれて、併せて過去に起きたトラブルや契約の際の注意点についても注目が集っており、依頼する側も事業者の健全性や透明性について心配しているのが実情です。
特に死後事務委任契約などは、契約してから何年、人よっては何十年も先に履行されるもののため、そうした利用者の不安を取り除き、安心して任せてもらえる事業者であると伝えるためには、事業者自身が専門性を有しているか、またはそうした知識を有している専門家がバックアップしてくれる体制であることを示していく必要があります。
結論として、身元保証事業や死後事務委任を受託するにあたって、特別な資格は必要ではありませんが、事業を円滑に進めていくにはそうした知識や専門家との連携は必須となるということです。
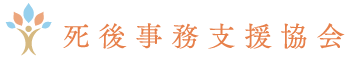


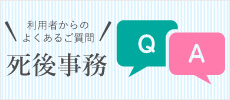

.png)
