ブログ
2021.07.12
遠方に住んでいる相続人からの死後事務代行のご依頼
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。梅雨明けも近いとあって夜中の気温も高いままですね。
高齢者の方は夜間のトイレを嫌がって寝る前に水分を摂ることを控えてしまう傾向にありますが、寝る前の一杯の水が熱中症を防ぐことに繋がることもありますので、冷房も効果的に活用して熱中症にならないよう対策していってください。
特にひとり暮らしの高齢者は熱中症になっても誰にも気づいてもらえず亡くなってしまうケースがこの季節は急増しますので厳重注意です!
さて、先日そんなおひとり暮らしの方が孤独死したご家族からご相談頂いた案件があります。九州地区にお住まいの方から愛知県で暮らしていたおひとり暮らしの兄弟が孤独死状態で見つかったとのこと。
現在は警察にてDNA鑑定中だが、鑑定が出た後の死後事務を丸っと任せることはできないか?というご相談です。依頼内容としては、
・DNA鑑定が終了した遺体の警察または葬儀業者からの引取り
・死体検案書の取得
・葬儀の代行(喪主の代行)
・遺骨の郵送手配
・各種行政手続き
・遺品整理
・財産整理と財産目録の作成
・遺産整理業務 等々
もちろん大丈夫です。
死後事務支援協会では通常依頼者本人との「死後事務委任契約書」に基づいて、依頼者の死後の発生する上記の内容のような死後事務を家族に代わって代行しておりますが、家族からの依頼でももちろん手続きは可能です。
本来、死後事務というものは家族が行うべきものを、近年の単身者や未婚者の増加を背景に疎遠な親族関係から、死後の手続きを行ってくれる家族がいない方が増えてきた為、家族に代わって死後事務を行う死後事務委任契約の需要が増えてきました。
そうした方々の死後に発生する手続きを親族以外の方が故人の遺志を尊重した形で行えるように整えたのが「死後事務委任契約書」であります。
ですので、死後事務を行う意思のあるご家族がいるなら、当然ご家族が行えば良く、第三者が手を出す必要はありません。
ただ、このコロナ禍で県を跨いでの移動が憚られる中、高齢の親族が慣れない土地で死後事務を何週間にも渡って行うのは体力的にも精神的にも非常にハードなのは間違いありません。
場合によっては、死後事務を行っている親族が倒れてしまうということにもなりかねませんので、そうした場合は私たちのような死後事務の専門家にご依頼頂ければ、ご家族に代わって必要な死後事務を全てご家族に代わって行うことが可能です。
私たちからすれば、もともと相続人がいない場合を想定した上で、依頼者本人が亡くなった後の手続きを法律上瑕疵の無い形で進めていくのが普段の業務となりますから、むしろ正式な権限を持っている相続人からご依頼頂けるのでしたら、普段の業務よりもトラブルなくかつスピーディーに手続きを進めることが可能となりますので、仕事としてはやりやすいくらいです。
コロナで長距離の移動が難しい、高齢で体力的に手続きが不安だ、疎遠な親族だったからなるべく簡便に手続きをすませてしまいたい。
といった、なるべく親族に負担の少ない形で死後事務を行っていきたいとお考えでしたらいつでもご相談ください。
死後事務、相続、遺品整理専門の士業がご相談に応じております。
2021.07.10
自筆証書遺言の検認と銀行での手続き
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
今日の名古屋は久々の快晴です。来週は梅雨明けも期待できるとのことで、待ち遠しい限りです。しかし、梅雨が明けたら明けたで今度は熱中症の危険も一気に高まってきますので、おひとり暮らしの方は特に注意してくださいね。
さて、先日来より死後事務を進めてきました緊急依頼で受任した案件についてです。依頼者の方は受任してから1月程で亡くなった為、事前の準備は完璧とまではいかなかった案件です。
しかし、そうしたケースは死後事務委任を行っていく中では珍しくはないもので、出来うる限りの対応を求められるのもまた事実です。
この案件は依頼者の方から連絡をもらった段階では既に依頼者にて大半の整理を進めていたこともあり、死後事務についてはそれほど煩雑な手続きはなく、通常のご依頼と同じ流れで進めることができました。
ですので、葬儀や遺品整理、行政手続きといった内容は数週間で全て終わっていました。(携帯料金や介護費用の還付金等はもう少し時間が掛かりますが、、、)
そうなってくると、後は費用の清算ということになります。清算にあてる費用は基本的に故人の遺産からとなります。死後事務委任契約では「預託金」として予め清算等に必要な金銭を預かるという方法を採られている事務所もありますが、当社団では原則預託金は預かりませんので、清算に必要な金銭は遺言執行者として故人の預貯金の払戻し手続きをした上で支払うこととなります。
しかし、金融機関での預貯金の払戻し手続きは通帳と印鑑を持っていけば応じてもらえるような簡単なものではなく、銀行所定の用紙に必要事項を記入し、故人と相続人の戸籍を集め、かつ手続きする人間が解約する権限を持っているのかどうかの審査を経て初めて解約に応じてもらえるものとなり、実際に解約金の払戻しを受けるまでにはけっこうな時間が必要となります。
特に今回のご依頼のような「自筆証書遺言」のケースでは、公正証書遺言や自筆証書遺言の保管制度を使用しているケースとは異なり、「家庭裁判所の検認手続き」という段階を踏まないと、銀行での受付はしてもらえません。
家庭裁判所での検認手続きとは、遺言書を発見した人や保管していた人などが、自筆証書遺言を家庭裁判所へと持っていき、家庭裁判所にて遺言書がどのような形で保管されて、どういった経緯で発見され、そして発見された遺言書はどういった物だったかを記録しておき、後々の遺言書の改ざんなどに備えておく手続きとなります。
この検認手続きを終えると、遺言書に「検認済み」の用紙を合綴されて返却されますので、これでようやく銀行などで手続きが可能となるわけですね。
ただ、この検認手続きを家庭裁判所に申請するのにも故人や相続人の戸籍を集めないといけませんし、特に死後事務委任契約を依頼される方の場合は、直系の相続人がおらず、相続人が兄妹姉妹となるケースも多く、戸籍を集めるのも一番時間が掛かる場合がほとんどです。
今回のご依頼でもそうした戸籍を集めて、家庭裁判所の検認も無事終わり、後は金融機関で預貯金の払戻しを行うという段階になったのですが、ここでひとつ不安があります。
今回の緊急依頼では、依頼者の方の体力的な面から公正証書作成が間に合わないかもしれないと危惧して自筆証書遺言を作成して頂きました。
結果的にはこれが功を奏した形ではあったのですが、心配なのは自筆証書遺言に訂正が入っていることです。自筆証書遺言は文字通り、全文を自筆で書いて頂くことが基本となりますが、その分手軽に作成することが可能となります。
ただ、専門の公証人等が作成する公正証書遺言とは異なり、書き方を間違えたり、自筆証書遺言の要件を欠いていたりすると遺言自体が無効となってしまう危険もあるため、自筆証書遺言の作成にはそうした危険もあることを認識した上で作成する必要があります。
この自筆証書遺言を作成する上での危険のひとつが、書き間違えた際の訂正の方法です。自筆証書遺言を作成するケースでは、当然遺言の内容を書き間違えるということもあります。
書き間違えたなら書き直せばいいのですが、基本的に遺言書は鉛筆などの訂正の容易な筆記用具ではなぐ、訂正の難しいボールペンなどで作成されますので、消しゴムで消して書き直しということができません。
ですので、書き間違えがあった場合に一番良いのが、遺言書を最初から作り直すということです。つまり、書き間違えたなら、訂正するのではなく、最初から新しい用紙に書き直すということです。
なぜそのような手間をかけるのかというと、自筆証書遺言のケースではその訂正の仕方も全て法律で規定されており、訂正の方法を間違えてしまうと、その訂正は無かった物(書き間違えた内容が正規の内容になる)として扱われてしまうからです。
訂正箇所が軽微な間違いならいいのですが、遺贈する金額だったり、遺贈する相手の名前だったりを間違てしまうと大きなトラブルのもととなってしまう訳ですね。
そして今回のご依頼の際に作成して頂いた自筆証書遺言には訂正が入っています。ここまで散々言ってきたのに書き直ししなかったの?と思われるかもしれませんが、重篤な病の方の場合は一度書いた遺言書の内容を再度書き直し頂く体力が無いケースもあるのです。
認知機能には全く問題がなくても、体力的な面で自筆証書遺言を何度も書き直すことはできない、そういったケースがあります。
本来こうしたケースでは公証人の先生に病院へ出張してもらい公正証書遺言を作成してもらうのですが、コロナ禍で公証人が病院に入る許可がでなかったため、公正証書遺言を作成することができず、自筆証書遺言を作成するしかなかった訳です。
なんとか書いてもらった自筆証書遺言。できるだけ負担が無いように、事前の希望の聴き取りを行いなるべく簡潔で文章量を少なくした遺言書の原案を作成してはあったのですが、依頼者にとっては初めて作成する遺言書でもありましたので、一部書き間違えがありました。
しかし、書き直しをする程の体力的な余裕もないため、書き間違えた場所を訂正する方法で対応したのですが、震える手で訂正を行うため、文言を記載する場所が微妙にズレてしまっていたりします。
厳密に見たら訂正方法が間違っているとも取れますが、本人の意思はしっかりとわかるという内容でもあり、また、これ以上、訂正に訂正を重ねてしまうと余計に遺言書の内容が分からなくなってしまうため、訂正はそれ以上行わないことにしました。
実際問題として、訂正箇所は遺言執行者に関する部分でしたので、訂正が無効となっても家庭裁判所で遺言執行者の選任申請を改めてすれば良い部分でもあったという理由もあります。
そうはいっても、金融機関で「訂正無効!」とされてしまうと、再度遺言執行者の選任手続きなどで時間が掛かってしまうことになりますので、なるべく訂正した箇所を問題視されないように資料を整えて金融機関に持ち込みをいたしました。
結果、手続きを申請した金融機関は特に問い合わせをされる事もなく、全ての金融機関で問題なく解約に応じてくれてましたのでほっと一安心です。
ここで大事なのは家庭裁判所での検認手続きが無事終わったとしても、検認自体に遺言書の有効、無効を判定する機能は無いということです。
簡単に言えば、家庭裁判所で検認手続きが終わったからといって「この自筆証書遺言は有効な遺言書!」と認められる訳ではないということですね。
最終的にこの遺言書を有効な遺言書として扱うかどうかは金融機関毎の判断に任せられるわけで、場合によっては、この金融機関では解約に応じてくれたけど、あっちの金融機関では応じてくれなかったという事態にもなったわけです。
こうした心配をしない為にも公正証書遺言での作成をお勧めするところではありますが、緊急依頼ではそうもいってはいられません。
死後事務支援協会では、病気や手術で急いで死後事務の準備を整えておかなければいけないといった「緊急依頼」にも応じておりますので、万が一の時はご相談くださいね。専門士業が駆けつけて対応いたします。
2021.06.01
ギリギリ間に合った遺言と死後事務委任契約
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の代表の谷です。6月に入り衣替えのシーズンとなりましたね。
普段から遺品整理の現場で作業着を着ていることも多い私ですが、やはり暑い時期にネクタイを締めるのは辛いものがありますので、今月からはノーネクタイでいきたいと思います。
さてさて、本日は死後事務委任契約書作成のお話しですが、コロナ禍においてこれまでは出来たのに、コロナ禍では出来なくなってしまった手続きというものがいくつかあります。その中で私たちの業務に関係してくるのが「遺言書」と「死後事務委任契約書」の作成です。
もちろん、遺言書や死後事務委任契約書が作成できなくなった訳ではなく、コロナ前とコロナ禍で出来なくなった、またはし辛くなった業務があるということです。
それはなにかというと、病院内での公正証書遺言や死後事務委任契約書の作成です。ご存知の通り、現在病院では病院内でのコロナ感染を防ぐために、多くの病院で面会禁止となっています。
ですので、重度の症状の方などでは一度入院してしまったら次に家族と会えるのは「お骨」になってからと言われるほど、感染対策としては徹底されている部分があります。
これは、多数の入院患者を抱える病院内でクラスターでも発生しようものならその被害は甚大な物となってしまうため、仕方のないことでもあります。
しかし、私たちのような遺言書や死後事務委任に携わる者からすると、この対策は依頼者にとって非常に難しい選択を迫ることになりかねないケースだとも考えています。
何故か?というと、遺言書や死後事務委任契約書という物は生前にご本人の最後の希望を記しておく非常に重要な書類となります。
遺言書で言えば、遺言者の方の財産を誰にどのように渡すのかという意思表示が含まれますし、死後事務委任契約書で言えば、万が一自分に何かあった場合には、葬儀や遺骨をどうして欲しい、または遺品整理や自宅の処分をこのようにして欲しいといった、依頼者の最後の希望が書かれている書類となる訳です。
極端な話し、遺言書にしても死後事務委任契約書にしても、本人の「最後の意思表示」と言えるものであり、特に遺言書は法律で定められた通りの要件に従って作成しなければ、「無効」(遺言は無かったものとされる)となってしまう大変重要な書類でもあります。
ですので、多くの専門家が遺言書は無効になる危険性が少ない「公正証書」で作成しましょうと口をすっぱくして言うところではあるのですが、これが現在病院内で作成できなくなっています。
コロナ前であれば、例え重篤の方であっても自分の意思を表明できる程度の能力が残っていれば、公証人の先生が病室まで出張して「公正証書遺言」を作成してくれました。
これは例え、手が動かない、言葉が離せないといった症状がある方でも、公証人の代筆や筆談といった方法でもって作成することができましたので、ある意味最後の意思表示をする機会が平等に与えられているとも言えます。
しかし、この最後の意思表示をする機会がコロナ禍での病院では失われてしまっているのが実情でもあります。
先日ある、肝臓がんを患っている方から緊急のご連絡を頂きました。年齢はまだ60代の方で本来なら第二人生をこれから謳歌していてもおかしくないような方です。
ご相談内容としては、死後事務を託したいという内容ですので、それだけなら普段のご依頼内容と変わりありません。しかし、この方には残された時間が少ない。
ご相談者いわく、医者も既に手の打ちようがない状態で、もって1ヶ月位だろうという病状らしく、実際に面談させて頂い際はお腹には腹水がかなり溜まっているような状況でした。
通常、死後事務委任契約を結ぶ際はご本人様から希望内容の聴き取りや費用の概算、実際の契約書の下書き等を確認して頂く為に何回か面談をさせて頂きながら作成を進めていきます。
しかし、お電話で最初のご相談を頂いた段階で、この方は緊急性が高いことが分かっていましたので、通常通りの手続きでは、間に合わない可能性があります。
そうした場合は、公証人役場に相談すると可能な限り早く公正証書の作成の準備に入って頂けるのですが、この方の場合は既に入院が目前に迫っている状況でもありました。
上でも述べた通り、コロナ前でしたらそうした場合でも入院病棟に公証人の先生が来て頂けて手続きを進めることができたのですが、今回は入院予定先の病院に確認したところ「病棟への入室は一切禁止」とされてしまい、公証人の先生に来て頂くことができません。
病棟に入る前のロビーなどでの作成も検討したのですが、こちらも特別な許可がなければ不可とされてしまい、実質病院内での公正証書の作成は出来ないこととなってしまいました。
では、どうするのか?というと、まずは本人の意思を公正証書以外の書面で残すことが必要です。遺言や死後事務委任契約書という書面は、公正証書でなければ効果がでないという訳ではありません。
むしろ、自筆で書かれる「自筆証書遺言」や一般契約書で作成される死後事務委任契約書の方がその利用率は高いかと思われます。(ただし、遺言書が無効になったり、不明確な死後事務内容になったりする恐れ有り)
公正証書を作成する予定であっても、公正証書を作るまでには印鑑証明書や戸籍の取得、証人2人の確保、公証人の先生との日程調整と、作ろうと思っても即日作成できる物ではありません。
しかし、そうした準備をしている間に体調が悪化して亡くなってしまっては、せっかくのご本人の意思を実現することができなくなってしまうため、公正証書の作成が間に合わなかった場合の保険として自筆証書遺言と一般契約書での死後事務委任契約書を作成しておくことが非常に大事となります。
今回の方も入院は腹水を抜く為の一時的な物であったので退院してから、または入院中でも外出許可を取っての公正証書遺言の作成を目指し、万が一に備えて面談させて頂いた際に自筆証書遺言と死後事務委任契約書の作成を行うという方法で対応しました。
幸いご本人様の遺言や依頼したい死後事務の内容は明確に決まっていましたので、自筆証書遺言と死後事務委任契約書の作成は無事終わりました。
しかし、後はご本人さんの体調の良い日に公正証書の作成をと段取りをしていたのですが、入院先の病院から死亡の連絡が入るという結果に。
残念ながら公正証書での作成には至りませんでしが、念の為にと作成しておいた遺言書と死後事務委任契約書が保険としての効果を発揮する形になった事例となります。
今回の方は自分の病状を正確に把握しており、それに向けてご自身がどうしたいのかをかなり明確にされていましたので、公正証書にする事は叶いませんでしたが、自筆証書遺言や死後事務委任契約書はすぐに準備することができました。
もし、これが入院した後に病院からのご相談の連絡となっていたら、コロナ禍では対応できなかったかもしれません。
ワクチン接収が進めば、こうした病院の厳格な感染対策も緩和されると思われますが、まだまだ予断を許さない状況でもありますので、心配な事があれば専門家の方へなるべく早い段階で相談するようにして頂ければと思います。
死後事務委任のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ。
2021.05.31
火葬後の遺骨を持ち帰らない(収骨しない)という選択
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の代表の谷です。
私の周りでもコロナのワクチン接収が始まっていますが、私の身近な方ではコロナに罹る人がいなかったのに、ワクチン接収が始まるのと機を同じくするように私の周りでもコロナに罹る人が増えてきています。
ワクチン接収という人類の反抗作成にコロナウイルスが徹底抗戦しているようで、まさに人類とウイルスの戦いみたくなってきていますね。
まずは自分がコロナに罹らないようにする。結果的にそれが感染の拡大を防ぐことに繋がりますますので、あと一息がんばりましょう!
さてさて、本日の話題は収骨についてです。
日本では基本的にご遺体は火葬されますので、当然火葬後に「焼骨」が残ります。焼骨を喉仏の説明などを聞きながら骨壺に収めるのが「収骨」(骨上げ)となり、これまではごく当たり前のように行われてきていました。
東日本と西日本では、「全収骨」か「部分収骨」かで地域によって、火葬後の焼骨を全て骨壺に収めるか、喉仏のように主要な骨だけを骨壺に収めるかで収骨の方法に違いがあります。
主に東日本では「全収骨」の地域が多く、西日本は「部分収骨」の地域が多いとされています。私が住んでいる名古屋なんかは「部分収骨」となります。
全収骨の場合は、骨壺に全ての焼骨を入れて遺族がお墓に埋葬したり、納骨堂などへ納めたり、最近では海や山への散骨なんて方法もあったりしますが、基本的には遺族がお骨の全てをどうするかを決めることになります。
しかし、部分収骨の地域では初めから一部のお骨は火葬場(斎場)にて処理することが前提となっていますので、遺族が持ち帰るお骨は全体の一部だけとなります。
では、遺族が持ち帰るお骨以外はどうなるの?というと、各自治体にて最終埋葬地にての供養に回されることになりますが、では最初から全ての遺骨を持ち帰らないという選択は可能なのでしょうか?
これに関しては各自治体の条例によって決められていますので、お住まいの地域によって収骨をしないといけない地域もあれば、最初から収骨をしないという選択ができる地域もあるということになります。
西日本はもともと部分収骨が多い地域ですので、収骨をせずに焼骨は全て火葬場(斎場)にて処理をしてもらうという方法も取りやすいということになります。
実際、今回私が死後事務委任契約にて担当させて頂いた依頼者の方も「収骨なし」を希望されており、そのように執り行ってきましたので、ちょっとだけ紹介しておこうかと思います。
私たちが死後事務委任契約を結ぶ際に特に重点的に確認するのが、「葬儀の方法」「遺骨の行方」「それらに掛ける費用」という部分です。
ここを曖昧にしておくと後々遺族が現れた場合にトラブルの元となりますので、私たちも依頼者の希望を確認しながら、予算や依頼者の希望などを確認していきます。
遺骨の扱いについても、「生前に建てておいたお墓へ入れる」「先祖代々の墓へいれる」「納骨堂へ入れる」「散骨する」等と、依頼者によって当然希望も変わってきますので、それに合せて契約書を作成するのですが、今回のご依頼者の方はそもそも「収骨をしない」という選択をされました。
お墓や納骨堂、散骨など今ではいろんな供養の方法がありますが、必ずしも遺骨をそうした場所へ納めて供養に回さなければいけないという訳ではありません。
無宗教の方で長期間に渡って供養することに疑問に感じている方、遺骨を残すことで管理の手間や親族への負担を心配される方、経済的な面からそうした手段を取り辛いという方など、以前まではお墓に入れるのが当然と思われてきたお骨の扱いも近年はだいぶ考え方が変わってきています。
そうした中、「収骨をしない」という選択肢も検討されてきているということですね。今回ご依頼頂いた方は親族が残っておらず、ご遺骨を残してもお墓参りに来られる方もおらず、また先祖代々のお墓というのもない状態で、今から自分のためだけのお墓や納骨堂を購入するという状況ではなかった方でもあります。
そうした場合でも、私たちがお付き合いのあるお寺などの合祀墓などへ入れるという提案もさせて頂くのですが、それもピンとこなかったのか、最終的なご依頼は「収骨なし」でのご依頼となりました。
私たちとしては、依頼者の方の生前の要望を契約書に記載されている通りに進めていくのが死後事務受任者の義務でもありますので、依頼者の方の希望がはっきりとしているのならそれに従うまでです。
では、実際に「収骨なし」とはどのように行うのかというと。まずは、利用する火葬場(斎場)が「収骨なし」に対応しているのかの確認をします。これは斎場を管理する役場の部署などに確認すれば教えてくれますので、電話などで簡単に確認できます。
次に費用が掛かるのかどうか。「収骨なし」に対応している火葬場でも、焼骨の処理に費用が掛かる地域と無料で行ってくれる地域とがありますので、念のため「収骨なし」ができるかどうかの確認と一緒に費用も確認しておくとよいでしょう。
実際の手続きについては、各自治体によって変わると思いますが、名古屋の八事斎場では葬儀を依頼する葬儀業者に事前に「収骨しない」旨を伝えておけば、後は葬儀業者の方が手続きを行ってくれました。
私も念の為、役場の担当部署へ「収骨なし」の可否、「費用」の有無、「事前の手続き」の方法などを電話で確認したのですが、その際は火葬前に火葬場にて事前に書類を提出するようにと言われました。
ただ、実際にはその書類も葬儀業者さんにて手配してくださっていたようで、私自身は火葬炉への立ち合いを行うだけで書類への記入等は行いませんでした。
後は、ご遺体を火葬した後に焼骨を「確認するかしないか」を決めておくと良いでしょう。名古屋の八事斎場では「収骨なし」を依頼することは可能で費用も掛かりません。
ですので、葬儀業者の方がご遺体を搬送し、正面玄関から火葬炉へと移動、最後のお見送りをした後は、その後の手続き(遺骨の処理)は全て火葬場(斎場)にお願いすることも可能です。
また、「収骨なし」を選択したとしても、火葬が終わった後に焼骨を確認することも可能ですので、火葬している間、待合室で通常の火葬と同じように待機して、焼骨を確認して、それから収骨はせずに、後の処理を火葬場に依頼するという流れも八事斎場では可能でした。
今回のご依頼者の方の火葬にあたり、斎場の方に「収骨なし」を選択される方は増えているのか?と聞いてみたところ、コロナの影響かはわかりませんが、「増えている」とのことでした。
月に「収骨なし」は何件くらいあるのか?と聞いてみたところ、だいたい2桁にいかないくらいということでした。火葬されるご遺体の数に比べればまだまだ少ない割合ですが、斎場の担当者の感覚ですと増えてきているという感想のようでしたね。
「ゼロ葬」などの言葉が注目されるあたり、死後事務委任を考える方以外の一般の方であっても、今後はこうした「収骨をしない」という方法を選ばれる方が増えてくるかもしれませんね。
死後事務支援協会では、ご家族の葬送支援として収骨をしないシンプルな葬儀プランを提携葬儀社の協力のもとご提供しています。
お墓や納骨堂などを用意せずに、シンプルな葬儀を執り行いたいという方はご利用ください。
死後事務支援協会のゼロ葬プラン
死後事務支援協会では、葬儀業者提携のもとゼロ葬プランをご用意しております。葬儀だけでなく行政手続きや相続人調査などもセットになっていますので、葬儀後の相続手続きをスムーズに開始したい方に最適なプランとなります。
| ゼロ葬プラン | お墓不要のシンプルな葬儀 |
|---|---|
| 内 容 | ・直葬 ・収骨なし(収骨も可) ・行政機関への届け出 ・葬祭費申請 ・相続人確定手続 (故人の出生~死亡までの戸籍収集) ・相続相談 |
| 費 用 | 253,000円 (税込み) 国民健康保険加入者は葬祭費から5万円の支給有り 葬祭費の代行請求はプランに含まれています。 ※ 孤独死案件等、警察でDNA鑑定を行っているご遺体の場合は別途「死体検案書」の発行手数料が実費で発生いたします。 |
| 対応エリア | 名古屋市及び名古屋市近郊 |
| 備 考 | 直葬は提携葬儀社の直葬プランとなります。 必要に応じて喪主の代行も行います。 名古屋市外でのご依頼の場合は交通費が別途発生いたします。 |
※ゼロ葬プランご利用希望の方は事前連絡をお願いいたします。
※行政機関への届け出は、死亡届の提出代行、14日以内に手続が必要な健康・介護保険・年金の受給停止等の死亡手続き及び必要書類の返却手続きとなります。
※県外などでご利用希望の方でもご相談に応じます。
死後事務委任契約をもっと詳しく知りたい!

2021.05.10
夫婦や兄妹で死後事務委任契約を結び、片方が存命の場合は死後事務を発効させない契約形態について
お久しぶりです。死後事務支援協会代表の谷です。コロナが依然として猛威を振るっておりなかなか前のようなノーマスクでの生活やみんなで楽しく会食といったことが難しい状況で今年のG・Wも終わりましたね。
海外に比べればまだマシともいえる日本の状況ではありますが、ワクチン接種までなんとか罹らない、うつさないように徹底した感染対策をしていきましょう。これは国や市町村の対策だけではなく、もう自衛するしかないことですので、まずは自分の感染対策を徹底的にですね!
さて、そんなコロナの心配が続く中ではありますが、先日ご契約した死後事務委任契約の事例が今後は増えてくるかもしれないと考えてちょっとご紹介をしておこうかと思います。
一般的に死後事務委任契約というと、「身寄りの無い方が信頼できる第三者に自分の死後の手続きをあらかじめ委任しておく」というイメージです。
そうした場合にすぐに思いつくのが、「単身者」「独身者」「おひとり様」といった、おひとり暮らしをされており、身近な親族が近くにいないといった方々かと思われます。
しかし、実際の死後事務委任契約では、「天涯孤独」という方は稀で、親族はいるけれど疎遠だったり、仲が悪かったり、音信不通だったりと、事情は様々ですが本来死後事務を執り行うべき方がいるけれど、頼りにすることができないので、第三者に死後事務を託すというケースが多くあります。
さらに今回ご紹介するのが、ご夫婦で死後事務委任契約を結んでおくケースです。
ご夫婦で死後事務委任契約を結んでおくと聞くと、夫婦の一方がもう一方の死後事務委任を行うようにも聞こえますが、実際には夫婦がそれぞれ、第三者と死後事務委任契約を結ぶということです。
少し分かり辛いと思いますので、下の図を参照してください。

上の図のように、まずは夫婦で死後事務委任契約をそれぞれ、信頼する第三者と結びます。
その後、ご主人様が亡くなったとすると、いまだ奥さんはご健在ですのでわざわざ第三者が手続きを行わなくても、奥さんが葬儀の手配やその後の手続きご自身の判断で行うことが可能です。
その奥さんも亡くなった場合には、死後事務を行うご親戚等がいないということで、ここではじめて最初に結んだ死後事務委任契約が効力を発揮して、信頼する第三者が死後事務に着手するという流れです。
上のようなケースはどういった場合に利用するのか?
例えば、夫婦ふたりで生活されているけれどお子様もなく、死後事務を託せるような親戚もいないといったような場合です。
なぜ、夫婦ふたりが揃って死後事務委任契約を結ぶのか?
夫婦ふたりで生活している段階では、片方が亡くなっても、生存配偶者にて死後の手続きは可能です。だったら、配偶者が亡くなった段階で死後事務委任契約を結べは、契約するのは1契約だけで、費用も抑えられるんじゃないの?という疑問が出てきます。
もちろん、その通りなのですが、わざわざ夫婦ふたりが事前に死後事務委任契約を結んでおくには訳があります。例えば、配偶者が亡くなった段階で生存配偶者が新たな契約を結べる状況とは限らないということ。
つまり、片方の配偶者が亡くなった段階で死後事務委任契約を結ぼうと考えていたとしても、その段階では生存配偶者も認知症等で新たに契約を結ぶことができる状況ではなくなってしまっていることもあるということです。
昨今は平均寿命も延びて元気な高齢者も沢山いらっしゃいますが、将来の事はやはりわかりません。ですので、万が一に備えて元気なうちに死後事務委任契約を夫婦がそれぞれ結んでおき、例え配偶者が亡くなった段階で認知症等で自分の意思能力が無くなってしまっていたような場合でも安心して過ごせるように準備しておくということですね。
どういった契約形態になるの?
先にも述べた通り、夫婦ふたりでまずは死後事務委任契約を結んで頂き、どちらが先に亡くなっても大丈夫な状況を準備します。
その際に、死後事務委任契約書に、生存配偶者にて死後事務が執り行える場合は先に亡くなった方の死後事務委任契約は無効となる文言を入れておきます。
そうすることによって、先に亡くなった方の死後事務委任契約書は無効となりますので、作成費用等は無駄になってしまいますが、故人と第三者の間で結んだ死後事務委任契約書は効力を発揮せず、生存配偶者の判断で葬儀などを実施することができ、また、契約をたてに第三者が無理やり死後事務を執行するといったことも防ぐことができます。(当然第三者に報酬等を支払う必要もありません)
無効になる死後事務委任契約はあくまで、故人と第三者で結んだ死後事務委任契約ですので、生存配偶者の死後事務委任契約まで無効になるわけではありません。
ですので、その後、生存配偶者が亡くなった段階では依然として有効な死後事務委任契約書となりますので、最後に亡くなった方の死後事務委任契約は信頼する第三者の手によって問題なく執行してもらえるということになります。
少し迂遠な方法にも思えますが、夫婦そろって80歳を超えるような高齢のご夫婦のような場合では、どちらが先に亡くなるかわからないし、ひとりになってからでは対策を考えられるほど、元気ではないかもしれないといった心配があります。
そうした場合には保険という意味でもこうした方法を元気なうちに準備しておくというのも有効な選択肢のひとつとなり得ます。長生きできる社会になったからこそ必要となる備えかもしれませんね。
死後事務に関するご相談は死後事務支援協会までどうぞ~。
2021.03.24
アサヒサンクリーン様にて遺品整理・死後事務の勉強会講師を務めてまいりました。
おはようございます。一般社団法人死後事務支援協会代表の谷です。
春爛漫といった感じで桜が咲き誇っていますね。いまだコロナの終息はみえておりませんが、日本人としては桜をみると気分が癒されます。来年はマスクなしで花見ができると最高ですね!
さてさて、コロナ禍ということもあり最近はセミナーや勉強会なども自粛につぐ自粛でしたが、名古屋では緊急事態宣言も解除されて、ぼちぼちと各所で勉強会などが開催されはじめています。
私も先日久々に講師を務めてまいりました。今回は訪問入浴・訪問介護で人気のアサヒサンクリーン様にお呼び頂き、ケアマネージャ向けの遺品整理と死後事務委任契約についての勉強会の講師となります。
当初は愛知県のケアマネージャだけで勉強会を実施する予定でしたが、コロナ禍ということもあり、ZOOMで勉強会を実施することになりました。
普段は皆さんの顔を見ながら話していますので、ZOOMで講師を務めるというのは初めての経験です。大勢の人の前で話すのはそれはそれで緊張しますから、ZOOMもありかな?と思い資料作成をして下書きを担当の方にお渡ししたところ、何故か愛知県以外のケアマネさんも参加する全国研修に、、、、。
なんでも下書きを責任者の方に確認してもらったところ、せっかくZOOMで行うなら他の地域の方にも見てもらおうという事になったようです。(緊張で私のガラスのハートがピンチです。。。。)
とはいえ、せっかくZOOMという便利なシステムもあることですし、私自身の負担は何も変わりませんので喜んでZOOMでの勉強会を実施させて頂きました。
勉強会の内容としては主に下記のような内容となります。
・遺品整理の際の注意点と遺品整理業界で問題になっている事柄などの裏話し的な話し。
・おひとり様問題に強い効果を発揮する死後事務委任契約の概要と実際の事例を通した死後事務委任契約の運用方法について。
このブログでも度々書かせて頂いていますが、遺品整理業界は遺品整理を始めるだけならなんら資格のいらない誰でも始めることができる仕事の反面、そうした参入障壁の低さからトラブルも多発しています。
今回の勉強会では、そうしたトラブルが起きる原因や実際の事例、また遺品整理を行う際の注意点などを私の経験した内容を基にお話しさせて頂きました。
また、後半では、単身者が増加するなかで問題になってくる死後の事務手続き問題とそれを解決する死後事務委任契約の概要の説明と死後事務委任契約の契約から執行までの流れを実際の事例をもとに説明させて頂きました。
なにぶん人前で話すのが苦手な性分なため、聞きづらい部分もあったかと思いますが、今回の勉強会を通してケアマネージャさん達の何か参考になる部分があったら嬉しい限りです。
最後は勉強会に参加された方々記念撮影をして本日の勉強会は終了です。お疲れ様でした~。
2021.01.31
愛知の身元保証を行うNPO法人の敗訴判決について
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。来週は立春ですね!寒いのが苦手な私としては春が待ち遠しい限りです。暖かくなるまでもう少しの辛抱です。コロナも含めて風邪などひかないように注意していきましょうね。
さてさて、昨日ネットのニュースを見ていたらこんなニュースが目に入りました。
「死後全額贈与の契約無効 身元保証の愛知のNPO敗訴」(日本経済新聞)
愛知県の安城市にて活動をしている身元保証を行っているNPO団体が、利用者との間で結んでいた死後に不動産を除く全財産を全額贈与するという契約を裁判所が公序良俗違反であるとして、全額贈与するとした契約は無効としたというものです。
また、判決の中ではNPO団体と市や社会福祉協議会との癒着の構造も認定しており、身元保証関連のトラブルにおいてもなかなかに根深い問題を含んでいるような内容にも見えます。
判決理由の中では「契約は不必要で内容も不明確。死後事務処理の費用は50万円ほどなのに、預金全額を受け取るというのは対価性を欠き、暴利と言わざるを得ない」とかなり強い口調で批判しています。
よっぽど、NPO団体側にて不正が行われたと思わせる事情があったのかと推察されますが、私的自治や契約自由の原則があるなかでここまで強く裁判所が批判するというのは珍しいのではないでしょうか。
ただ、死後事務支援協会においても、死後事務委任契約を通して身元保証を行うこともありますので、他人事ではありません。
もちろん、今回の事件のような契約内容が不分明で暴利をむさぼっているなどと言われるようなことは行っておりませんが、死後事務委任契約の特性上どうしてもトラブルが起きた時点では依頼者であるご本人は亡くなっていることとなり、本人の意思を再度確認するということはできません。
ですので、説明責任の重要性と契約の透明性の確保はなによりも大事と強く思い知らされるニュースでもありました。人の振り見て我が振り直せではありませんが、今一度注意喚起をするとともにご利用者の方にご満足いただける死後事務支援を行ってまいりたいと思います。
ご自分の死後の葬儀や遺品整理、各種手続きにて不安をお持ちの場合は死後事務支援協会までお気軽にご相談くださいね。
2021.01.20
死後事務委任契約からの不動産管理、売却までのお話し
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
緊急事態宣言が発令されていますが、コロナは終息の気配が見えませんね。感染者の増加に伴い入院やホテル等の療養施設への入所も難しいようですので、やはり一番の対策は「自分がコロナに感染しないこと」これに限りますね。皆さんもうひと踏ん張り頑張りましょう!
さてさて、今回は死後事務委任とそれに伴う不動産売却についてのお話しです。死後事務委任契約を結ばれる方の多くが基本的には全ての死後の手続きをご依頼されることになります。
もちろん、死後事務委任契約を結ぶからといって1から10まで全てを依頼しないといけないわけではありません。死後事務委任契約は委任契約ですので、依頼者と受任者で話し合って必要とする内容だけ依頼すればいい契約です。
しかしながら、死後事務委任契約を依頼される方の多くが、死後の手続きをしてくれる親族がいない、親族がいたとしても疎遠な関係、親族とは仲はいいけど遠方に住んでいるので迷惑をかけたくないなどの事情を抱えていらっしゃいます。
ですので、死後事務の依頼内容は遺体の引取りから、葬儀、納骨、未払いの治療費や家賃、公共料金の支払い、役場への届け出、遺品整理と基本的な内容は全て依頼した上で、後はご依頼者の個別の希望で、ペットの引取り先や山や海への散骨、菩提寺や福祉団体への寄付といった追加の内容を行っていくことになります。
そうした依頼の中でも比較的多くなるのがご自宅の売却です。賃貸物件でしたら遺品整理と原状回復を行った上で貸主と退去立ち合いを行って返却すれば完了となりますが、持ち家の戸建てやマンションとなるとすぐには解決できません。
もちろん、生前から自分が亡くなった後に不動産を相続させる相手が決まっているのでしたら、遺言執行者として遺言執行の一環としてサクサクと名義変更を行っていきます。
しかし、清算型遺言のように、自分の財産を全て売却した上で負債を全て支払い、残った財産を希望する先へと寄付したいといった要望の場合は、まずは買主を探さないといけないことになりますのでやはり時間はかかることとなります。
今回は死後事務委任契約のご依頼者が生前住んでいたご自宅のマンションを依頼者の相続人へと相続させる遺言であり、私が遺言執行者として指定されていましたので、相続人への名義変更は滞りなく完了しました。(実際に名義変更を行ったのは司法書士の先生ですが)
その後、全ての死後事務が完了して報告資料一式を持参して他県にお住まいの相続人のもとへ伺ったところ、相続した不動産を売却したいということとなり、また売却が終わるまでの間のマンション管理もお願いしたいとのことでした。もちろん大丈夫です!
不動産の売却については不動産会社に依頼をして、売却までの不動産の管理をこちらで行っていくことになります。
とは言っても、室内は既に死後事務の一環として既に遺品整理は終わっていますので、定期的な空気の入れ替えや、マンションですので定時総会や各戸の水道の高圧洗浄、火災報知器の点検といった立ち合いの必要な作業への協力、そして管理費、共益費、修繕積立金といった費用の支払いが主な内容となります。
管理内容としては複雑な物はありませんが、遠方にお住まいのご家族が行おうと思うとどうしても長距離の移動や交通費の問題もありますし、ご依頼頂いた時はちょうど1回目の緊急事態宣言が出るかどうかという時分で県を跨いでの移動という問題もありましたので、ご依頼頂くことで負担を軽減できたかと思います。
ご依頼頂いた後の管理と売却については、立地は名古屋でも非常に良い場所であり、繁華街に近い割にはお寺の傍で静かな環境、内装も数年前に入居する際に大きくリフォームしたばかりでしたので非常に綺麗な状況です。
普段ならすぐに買い手もみつかりそうな状況ではあったのですが、コロナ禍ということも影響したのか内見も少なく出だしはあまり良くなかった印象です。
ただ、そこは頼りになる不動産会社が独自のルートで買い手を探してくださり、当初予想していた金額よりもかなりの高額での売却が決まりました。これには依頼者である相続人の方にも喜んで頂けてこちらとしても一安心です。
そして昨日、最後の水道代の支払いを終え、管理業務も終わりとなり、お預かりしていた管理費用も相続人の方へとご返却してすべての業務が完了となりました。
死後事務のご依頼者が亡くなったのが昨年の1月ですので、不動産売却まで含めれば死後事務に着手してからちょうど1年掛かったことになります。ご依頼頂いた死後事務の内容自体は4ヶ月ほどで完了していましたが、不動産の売却が入ってくるとやはり長期間の業務になりますよね。
つくづく死後事務委任のお仕事はひとりでは遂行できず、今回お手伝い頂いた司法書士や不動産会社をはじめ、税理士や弁護士の先生、その他専門家の皆様といったチームでの遂行が欠かせない業務と実感するところです。
死後事務委任契約は、ご依頼者が亡くなった後に実行する契約ですのでご依頼者の希望通りに手続きを進めていくこと、また相続人はもちろんご近所の方やお世話になった病院、介護施設の方々へ迷惑をかけないようにしなければいけません。
今回もご依頼者の死後事務を無事終えることができ、相続人の方にも喜んでもらえたことで故人の想いを叶えることができたのかなと安堵しております。
死後事務委任契約のご相談でしたらいつでもお気軽にご相談くださいね。
2021.01.01
あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます!
令和も3年目となり、平成から変わった当時はよく書き間違えましたがさすがに書き慣れてきましたね。昨年はコロナで終わったような一年ではありましたが、今年はオリンピックが開催できるくらいに終息そしてアフターコロナでの経済の復活を期待したいものです。
死後事務支援協会では今年は新規のサービスとして短期身元保証を開始し、入院や手術の際の身元保証で困っている方や成年後見人としてこれまで仕方なく身元保証にサインしてきた士業の先生方のお力になれればと考えております。
本年も死後事務支援協会をよろしくお願いいたします。
2020.12.30
来年も良き年になることを願って
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
あっという間に年末になりましたね。毎年恒例の今年の漢字は「密」になったみたいですが、私は絶対に感染の「染」になると思っていただけに、世間との考えのギャップに愕然としました。「染」はランキングにも入っていなかったような、、、、。
ともあれ、今年はなんとか自分や周りの人にコロナに罹った人はおらずほっと胸をなでおろしているところではあります。しかしながら感染者自体は依然として増加しているわけであり、医療従事者の方々には頭の下がる思いです。本当にありがとうございます。
医療従事者の方々への負担を減らす一番の方法は、まずは自分がコロナに罹らないことですよね。自分がコロナに罹らなければ、当然他の人へ感染を広げることもありません。そうすることで結果的にコロナ患者が減っていくことで医療従事者の方々への負担も減らせることになります。
年末年始でお酒も入り気が緩むのも仕方のないことではありますが、今一度自分の身の回りから感染対策を徹底していきましょうね。
さてさて、今年も残すところ後わずかとなりました。今年は元旦の早朝から死後事務のご依頼を頂いている方が危ないという連絡を入所されている施設より頂き、夕方に様子を確認にいった後の夜間にお亡くなりになりました。
正月ということもあり、火葬場の手配など心配しましたが、葬儀業者さんの手助けもあり無事お送りすることができました。
また、その方の死後事務が大方片付いた頃には別の死後事務をご依頼頂いている方との連絡が取れなくなり、安否確認で様子を確認しに伺ってみると回覧板が複数溜まっているなど不審な点があったことから、急遽消防や警察へと連絡して室内を確認してもらったところご遺体を発見することになりました。
心臓の持病を心配されて死後事務に関するご依頼を頂いてはいましたが、まだまだ60代というお若い方でもありましたので、残念でなりません。
依頼者の方とはよく喫茶店でコーヒを飲みながら世間話や仕事に関しての話しをお互いにするなどとても良くして頂いていたので、その方のご自宅の近くを通る度につい癖でお茶でも誘ってみようかという思いが今でも沸いてきます。
私が遺体を発見する端緒とはなりましたが、実際にご遺体を発見したのは消防の方でもあるので形式的には「孤立死」という形になります。ですので、その後に事件性の確認などで鑑識の方がご自宅を調査しご遺体は警察にてまず回収されていきました。
ご遺体発見時に死後事務受任者であることを伝えてはありましが、警察としてもまずはご家族や親族へと確認した上でないと遺体を死後事務受任者に引渡しができないということで、ご遺体の発見から2週間ほど経ってからではありますが無事、事前にご指定頂いていました葬儀業者にて葬儀をあげてご遺骨は菩提寺へと納めることができました。
今年はお二人の方の死後事務ならびに遺言を執行することとなりましたが、新規の方との死後事務委任契約もありました。
コロナ禍でステイホームが叫ばれる中、高齢者に限らず持病を持った方々が家に引きこもっていたとしても「感染対策」と思われて異常に気付かれにくいということも起きています。
そうした結果、天涯孤独の方や親族と疎遠になっていたりと「死後事務委任」を必要とされているような方は、自分で積極的に外出したり、SNS等で発信したりしないと「自分は大丈夫です!」ということを周りに知ってもらう方法がありません。
ただ、高齢者の方は体調だったり、SNSの使い方がわからなかったりと、誰でも気軽にとはいきませんよね。
ですので、私たちのような国家資格を有する士業が「成年後見」や「見守り契約」、「死後事務委任契約」といった制度を使用しつつ積極的に安否確認を行ったり、不安や困り事への相談に応じることには大きな意義があると考えています。
「もし自分に万が一のことがあったら、いったい誰が自分の葬儀や納骨をしてくれるのだろうか?」という、これまでは漠然としか考えてこなかった事柄がコロナ禍において現実的な身近な問題として認識されてきています。
「自分にもしもの事があったらどうなるの?」という疑問に対しての答えは、その方の生活状況や家族構成、そしてなにより、ご自身としては「どうありたいのか」という考え方によって千差万別となります。
ここで挙げている「死後事務委任契約」もそうした疑問に対する答えのひとつでしかありません。場合によっては、遺言や家族信託なども併せて考える必要があったり、生前に税務対策などを考えておかないと相続人への負担が大きくなってしまうという方も見えられるでしょう。
今年のまとめとして思うところは、死後事務委任契約を結ばれていた方は手続きが非常にスムーズであり、やはり生前にどれだけ準備していたかで、家族や遺族へ掛かる負担を大きく減らすことができるようになるということです。
特に自分の死後の手続き(葬儀や納骨、遺品整理など)を疎遠な親族が行うと予想されるようなケースでは重要となります。
こうした疎遠な関係の場合は、自分にもしもの事があったとしても、本来葬儀などの死後の手続きをするはずだった親族が「相続放棄」をしてしまうことも考えられます。
実際に遺品整理の相談を受けている中でも「疎遠な叔父(叔母)が亡くなったのですが、遺品整理は私たちがやらないといけないのでしょうか?」というご相談を良く頂きます。
同じような相談でも「何十年もあってないので関わり合いたくない」「なんとかしてあげたいが先立つものがない」「賃貸物件で亡くなったので、大家さんから賠償請求が怖い」と抱えている事情は様々です。
いずれにしても、こうした疎遠な親族の場合はある日突然警察や役所より「○○さんが亡くなったので遺体の引取りをお願いします」と突然連絡が入ることとなりますので、まさに寝耳に水状態となり大変混乱することとなります。
こうした状況での相談者の中には「なんで私がこんな苦労をしないといけないのでしょうか!(怒))」と、憤懣やるかたないといった様子の方もいらっしゃいます。
そうした場合は専門家としては「相続放棄」という手段について説明することになりますが、親族が相続放棄をしてしまうと、今度は病院や施設、賃貸物件の大家さんなどが、未払いの医療費や施設利用料、未納家賃や遺品整理などで誰も支払いや片付けをしてくれないと困ることとなってしまいます。
こうした問題を解決する方法のひとつが「遺言」だったり「死後事務委任」であります。たとえ親しい家族がいなかったとしても、信頼できる第三者に事前に依頼しておくことで、自分の希望する通りに葬儀や納骨(散骨)を行い、その他の遺品整理や未払いの医療費や家賃などの支払いも専門家に依頼しておくことが可能となります。
そうすることで、仲の良い家族では死後の手続きで掛かる負担を減らすこともできますし、疎遠な親族しかいない場合は、一切の手続きを専門家に任せてしまい疎遠だった親族には迷惑を掛けないように準備しておくことができます。
こうした事前の準備はなかなか自分だけでは考えがまとまらないものですので、気になることがあればいつでもご相談ください。
死後事務支援協会は令和三年も死後事務や短期身元保証を中心として、おひとり暮らしの高齢者のサポートを頑張ってまいります。
最後となりましたが、今年一年誠にありごとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
一般社団法人 死後事務支援協会 代表理事 谷 茂
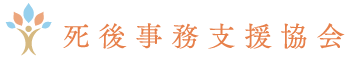


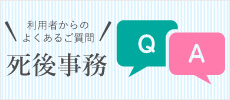

.png)
